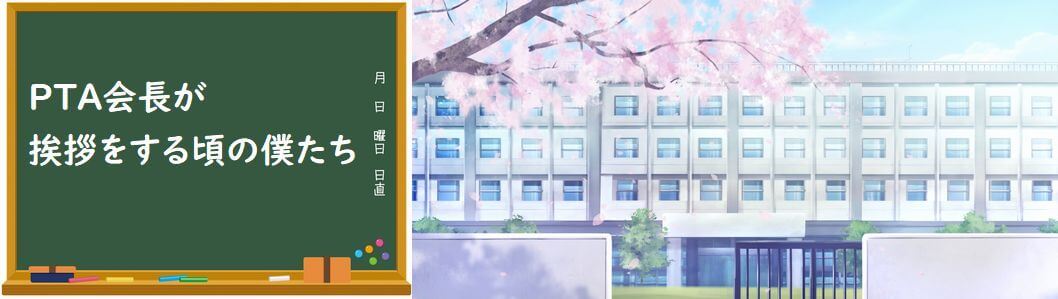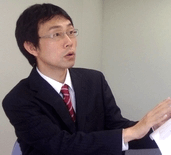2026/01/22
以下で、
卒業式の祝辞に「NGワード」はないですよ。あるのは「その場にふさわしい言葉」と「ふさわしくない言葉」の区別だけですよ。
というお話をしています。
卒業式の祝辞にNGワードはない。その場にふさわしいかで判断すべし。
https://www.ptakaicho-aisatsu.com/sotsugyoshiki-ng-word/
ここでは、では、それらをどう言い換えればいいでしょうか。
1. 「失敗しても気にするな」→「挑戦することに価値がある」
新しい経験には常にリスクがありますが、それでも踏み出す勇気こそが成長につながります。失敗を前提とするのではなく、挑戦する姿勢そのものを肯定する言葉に変えることで、前向きなメッセージになります。
2. 「もう二度と戻れない」→「ここで得た宝物をこれからも大切に」
学生時代に築いた友情や学んだことは、形を変えても人生の糧として残り続けます。喪失ではなく、獲得したものの価値を強調することで、過去を肯定しつつ未来へつなげる言葉になります。
3. 「現実は厳しい」→「これから多くの学びが待っている」
社会に出れば困難もありますが、それは同時に新しい発見や成長の機会でもあります。厳しさを強調するのではなく、学びの連続としてとらえることで、前向きな姿勢を育む言葉になります。
4. 「挫折を経験することになる」→「壁にぶつかったときこそ、本当の強さが育つ」
困難を予告するのではなく、それを乗り越える力が自分の中にあることを伝えます。試練を成長の機会として位置づけることで、卒業生に自信と希望を与える言葉になります。
5. 「学校生活が終わってしまった」→「新しい章が今、始まる」
終わりではなく始まりを強調することで、未来への期待感を高めます。人生は連続した物語であり、卒業はその中の大きな転換点であることを伝える言葉になります。
6. 「もう遊べない」→「人生の新しい楽しみ方を発見できる」
大人の世界にも、学生時代とは違った喜びや充実感があります。一つの楽しみが終わるのではなく、新しい楽しみが始まることを伝えることで、前向きな期待を持たせる言葉になります。
ここまで見てくるとお気づきかと思いますが、これらは言葉遊びの域を出ません。
たとえば、ふさわしくないとしている左側の表現も、前後の文脈次第で素晴らしいメッセージになります。右側の言い換えた言葉は、文字通り言い換えただけです。
結局のところ、「この言葉がいい」「この言葉が良くない」という視点で見るのではなく、どのようなお祝いの言葉を卒業生たちにプレゼントしてあげたいかという視点で見るほうが建設的なのです。
改めてになりますが、
その言葉を見て「これは良い、これは良くない」と形式的に捉えるのは無意味です。
言葉は単体で存在しているわけではなく、必ず文脈の中で意味を帯びます。大事なのは「言葉そのもの」ではなく「どういう意図で、どんな流れの中で伝えられるか」です。
形式的な言い換えに囚われるのではなく、心から伝えたいメッセージは何か。それを考えることこそが、卒業生の心に残る祝辞を作る唯一の道です。