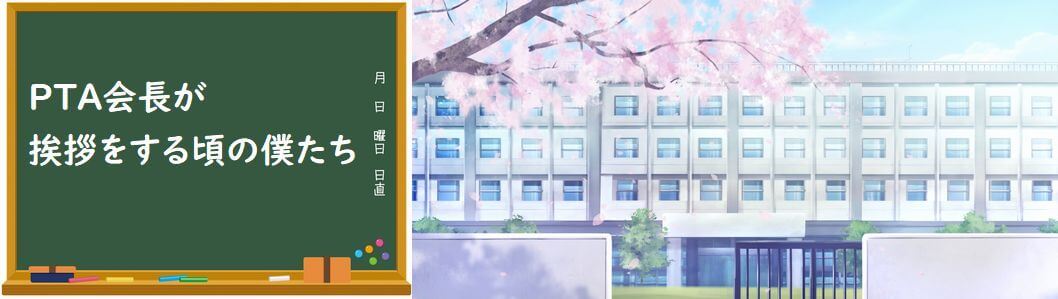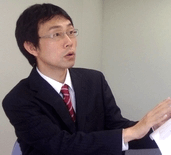2026/01/22
春の陽だまりに包まれた体育館。桜のコサージュを胸に、晴れやかな表情で座る卒業生たち。そんな彼らを前に、PTA会長が壇上に立つ。
「皆さん、卒業おめでとうございます。これからの人生、失敗を恐れず、自分の信じた道を歩んでください」
拍手が響く中、私はふと思った。
この言葉は、本当に卒業生たちに向けられたものなのだろうか。

卒業式での祝辞を聞いていると、時折、不思議な切実さを感じることがある。それは単なる儀礼的な挨拶を超えた、何か深い想いが込められているような気がするのだ。
「挑戦することの大切さ」「困難に立ち向かう勇気」「自分らしさを大切にすること」。PTA会長が語るこれらの言葉は、確かに卒業生への餞の言葉として美しく響く。しかし同時に、それは話し手自身の人生への省察でもあるのではないだろうか。
中年を迎えた大人が若者に贈る言葉には、しばしば自分自身への戒めや願いが含まれている。「もっと挑戦すればよかった」「あの時、勇気を出していれば」「周りの目を気にせず、自分の道を歩めばよかった」。
そんな小さな後悔を抱えながら、それでも前向きに生きてきた大人だからこそ、若者たちには同じ轍を踏んでほしくないという切実な願いがある。祝辞という形を借りて、実は自分自身に言い聞かせているのかもしれない。
しかし、これは決して悲しいことではない。むしろ、人生はいくつになっても学び直し、歩き直すことができるという希望の表れでもある。
卒業生に「自分の信じた道を歩んで」と語る時、その人もまた、残された人生で自分らしい道を歩み直そうと決意しているのだ。若者たちの門出を祝いながら、同時に自分自身の新たなスタートを切っている。
卒業式という場は、表面的には若者の節目を祝う場だが、実際にはそれぞれが人生について考える深い時間でもある。卒業生は未来への不安と期待を抱き、保護者は子どもの成長と自分の歩みを重ね合わせ、教師は教育者としての使命を再確認する。
そして祝辞を述べる人もまた、若者たちの姿に自分の青春を重ね、これからの人生への想いを新たにしているのだ。
はなむけの言葉が持つ二重の意味
「頑張って」「負けないで」「自分らしく生きて」。
これらの言葉は、卒業生への応援歌であると同時に、話し手自身への応援歌でもある。人生の先輩として若者に語りかける言葉が、実は自分自身への励ましや約束になっている。
そう考えると、卒業式の祝辞がなぜあんなにも心に響くのかがわかる気がする。それは建前や美辞麗句ではなく、一人の人間の正直な想いが込められているからなのだ。
次に卒業式で祝辞を聞く機会があったら、少し違った角度から耳を傾けてみてほしい。その言葉の向こうに、一人の大人の人生への想いや、小さな後悔と大きな希望が見えてくるかもしれない。
そして私たち聞き手もまた、その言葉を自分自身への餞として受け取ることができるのではないだろうか。人生はいつでも、新しい門出の連続なのだから。