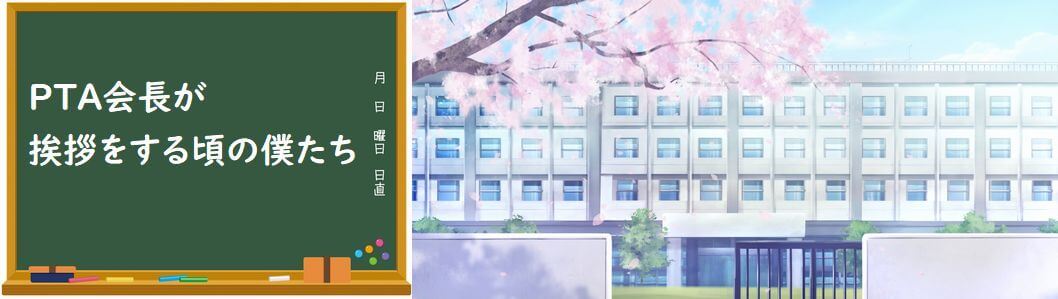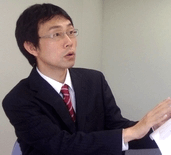2026/01/22
以下の例文をアップしました。
小学校 卒業式 PTA会長 祝辞 例文(少人数・縦割り授業・絆)
ここで、小学校がなくなる、厳密には、近隣の中学校と一緒になることを伝えている箇所があります。
ダメージは、ある。
実際、自分が卒業した小学校がなくなるって、卒業生たちにとってダメージゼロではないですよね。「自分が育った場所」「友達と過ごした空間」「思い出の詰まった建物」がなくなるというのは、あの教室の匂いとか、運動場の感触とか、下駄箱の位置まで、身体で覚えているような記憶が消えてしまうような感覚があります。
理屈では「思い出は残る」と分かっていても、実際には「帰れる場所」がなくなる寂しさが、静かに心に残る。特に小学校って、人生で最初に「社会の一員としての自分」を作っていく場所だから、なくなることの影響は意外と深いはずです。
だからこそ、PTA会長がどのように伝えるかが重要
学校がなくなるような節目では、PTA会長の祝辞は形式的なものではなく、「卒業生の気持ちに寄り添いつつ、未来への希望をどう言葉で橋渡しするか」という、とても繊細で意味のある役割になります。子どもたちは、校舎がなくなることを“寂しいこと”として感じている一方で、大人たちは「新しい学校でも頑張ってね」と励ましたい気持ちがある。卒業式でのPTA会長はその両方の感情をつなぐ存在になり得ます。
たとえば、
- 「この校舎で過ごした時間は、これからもあなたたちの中で生き続ける」
- 「新しい場所でも、この学校で育んだ絆や優しさを大切にしてほしい」
のように、喪失と希望を一緒に語る言葉が響きます。
あり続けるかどうかは自分の思いによって決まる
物理的にはなくなるけど、心の中にはずっと存在し続ける。これは学校だけじゃなくても、誰か大切な人との思い出も同じです。校舎や人の命のように、形あるものはいつか終わりがくるけれど、その中で感じたこと、誰かと過ごした時間、受け取った優しさや言葉は、自分の中で「どう生かしていくか」によって、ずっと続いていく。
たとえば、卒業生がその学校で学んだ思いやりや仲間意識を新しい場所でも自然と行動に表せたなら、それはもう、“学校が生き続けている”ってことになります。同じように、人との別れでも、「もういない」ではなく「その人からもらった何かを、自分が今も持っている」と思えるかどうかが、心の中での“あり続ける”ということなんだと思います。
12歳の卒業生たちだからこそ、やんわりと伝える
12歳は、まだ“子ども”ですが、心の中では確かに“感じている”はずです。ただ、大人の言葉で「存在とは」「記憶とは」と言っても、まだ整理して理解するのは難しい。だからこそ、やんわりと、でも本質はちゃんと届くように伝えることが大切です。
たとえばこんな感じの表現なら、子どもたちにもスッと入ると思います👇
こう言われると、難しい理屈ではなくて、「あ、そうか、自分の中にあるんだ」と自然に感じられる。子どもたちの“心の風景”に寄り添う言葉は、言葉を柔らかくしても、ちゃんと深く届くはずです。